colour1-2 橘田正造
2025年04月17日
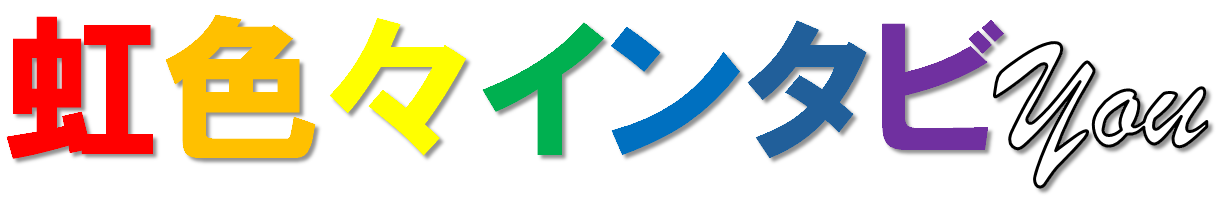
一人一色、八十億人八十億色――。地球上に存在する人の数だけ色があり、そのどれもが非常に興味深い輝きを放っています。地球同窓会では色々な人へのインタビューを通して、唯一無二の声色を発信し、世界中に虹をかけていきます。話のテーマは毎度変化!今回は…。
Colour1-2 地球社会共生学部・元教授
![]()
【#1「あの時、あの前、あの後――未知のウイルスとの遭遇から5年、船中の当事者に訊く」】
【#3「学部名の由来は?地球の長所・短所も熱く厚く掘り下げる!必読エピソード大連発!」】

長野生まれ、西宮育ち、青学大出身。世界中を飛び回った国際開発金融マンが新学部の初代教授になるまで
2015年に産声を上げた青山学院大学・地球社会共生学部は、2025年に10周年を迎えます。それを記念した特別プログラムの一環として、2015年から1期生が卒業する2019年まで教授を務めた橘田正造先生に、住居を構える藤沢でインタビューを実施しました。
20代後半でのバンコク(1977~79)を皮切りに、マニラ(1984~87)、デリー(1992~94)、パリ(2002~03)と各地で駐在員を務め、仕事で世界53か国を訪れた後、どのようにして母校の青山学院大学に戻り、地球の初代教授になったのか。生い立ちから語っていただきました。
――◆――◆――
【「世の中をちょっと甘く見ていた」高校時代】
1949年1月に、長野市の郊外で、川中島の合戦があった場所の近くで生まれました。皆さんの時代は病院で生まれるんだけど、僕らの時代はまだ母親の実家でお産婆さん、今でいう助産婦さんが取り上げていました。
父親は神戸で仕事をしていたので、生まれてすぐ、神戸に近い西宮に移りました。阪神甲子園球場のあるところです。そこで高校を卒業するまで育ちました。
高校の3年生の秋に突然、私の頭の中になかった父親の転勤がありました。既に勤務地は神戸から大阪に移ってはいたけど、大阪からどこかに行くとは思っていなかったなかでの東京転勤でした。私はたくさんの友達が進学する関西の大学に行くつもりでしたが、急に「お前東京の大学を受けろ」と言われ、それで先生に相談して、いくつか東京の大学を受けて、青山学院の経済学部に行きました。
それまでは世の中をちょっと甘く見ていて、「これぐらいやっていれば、慶應ぐらい受かるだろう」と思っていました。そんな感じで舐めてかかって受けたら駄目でしたね。当時の第1志望は国立で、第2志望が慶應、青山は第3志望でした。
周りも自分も阪神タイガースファンで、アンチ東京だから、東京の大学を受ける人はほとんどいなくて、成績上位者は京都大学など関西の国立大学に行っていました。自分はそれほど悪くない成績だったから「これくらいできれば、慶應ぐらいは受かるだろう」と思っていたけど駄目でした。それで浪人しようと思ったら、高3の時の担任が「いや、君は浪人して成功するタイプじゃない」と。自分自身がどういうタイプか僕は分からないんだけど。「受かったところに行きなさい」と言われたのをよく覚えています。
高校の時は、日本を豊かにするために商社に入って、日本の製品を売って外貨を稼ぐ仕事をしたいと考えていました。僕らの子どもの頃は、教科書に出てくる日本の統計数字はみんな先進国の中では低位で、日本が貧乏だったんです。例えば、人口1万人当たりの乗用車の台数は、アメリカやイギリス、フランス、ドイツと比べて、日本は極端に少ない。だから子供心にも「こりゃなんとかせにゃいかん」と思っていました。

〈青学大経済学部の原豊ゼミのOB会の時の写真です。当時私は早大大学院の修士課程1年目で満23才でした。真ん中の2人が原ゼミの1年上の先輩達で、左端が私と同期の男性で、オンワード樫山の社員でした。後に同社のブランド「23区」の商品化に成功して、若くして同社の副社長になったのですが、過労のためか40代前半で他界しました〉
【「これぐらいやっとけば大丈夫」からの脱却】
大学時代は2年生の夏、1968年の「プラハの春」事件がキッカケで、ソ連、東ヨーロッパ経済を勉強し始めました。社会主義の経済がなぜ停滞を始めたのか。やってみたら面白くて面白くて、「これは4年生で卒業したら中途半端だな」と。大学院に行きたくなって父親に相談したら、父親は「駄目だ。お前みたいな1人っ子の世間知らずは早く社会に出て鍛えられろ」と言うわけです。僕は諦められないから、父親と何度か話し合って、最後は母親が助太刀してくれました。
早稲田に堀江先生という、まさに僕がやりたいことを研究している先生がいて、それで早稲田の大学院を受けたんですよね。今でこそ文系で大学院に行くのは、そう珍しくないけど、僕らの時代は文系で大学院に行ったら、就職はほぼ不可でした。しかも、入試は大学卒業直前の年1回でした。受験に失敗したら就職浪人になります。「それでもお前行くのか?」と周囲に言われても、「とにかく研究したい」と。それで受けたら受かったんです。
それまでは中高大と受験して、みんな駄目でした。生まれて初めて自分でもっと勉強したくなって受験したら、早稲田の大学院に受かったんです。倍率は3倍でした。大学院に行ったらまたまた面白くなっちゃって。もうちょっと勉強して、博士課程に行こうかとも思ったんだけど、父親と「大学院は修士の2年だけ」と約束していたので、就職することにしました。国際貢献の仕事を探しました。
今でこそ、JICAとかがあるけど、当時はほとんどなくて、開発途上国に対する資金協力の政府機関がありました。低利で長期返済のローンを出して、インフラを整えたり、農村開発をしたりして、返してもらって、それをまた他の国に貸したりする。円で貸して、円で返してもらう。円借款をやっている組織があるのを知って、創立後まだ10年目ぐらいだったんだけど、駄目元で受けました。倍率は25倍。125人受験して、合格者は5人でした。受かると思っていなかったんだけど、受かっちゃいました。
だから自分で見つけた好きな分野の勉強を始めたら大学院に受かり、真剣に国際貢献の仕事をしたいと思って受けたらまた受かり。意識の差は本当に大きいと思います。高校生までは何となく「これぐらいやっとけば大丈夫だ」と甘く考えて受けて、みんな駄目でした。
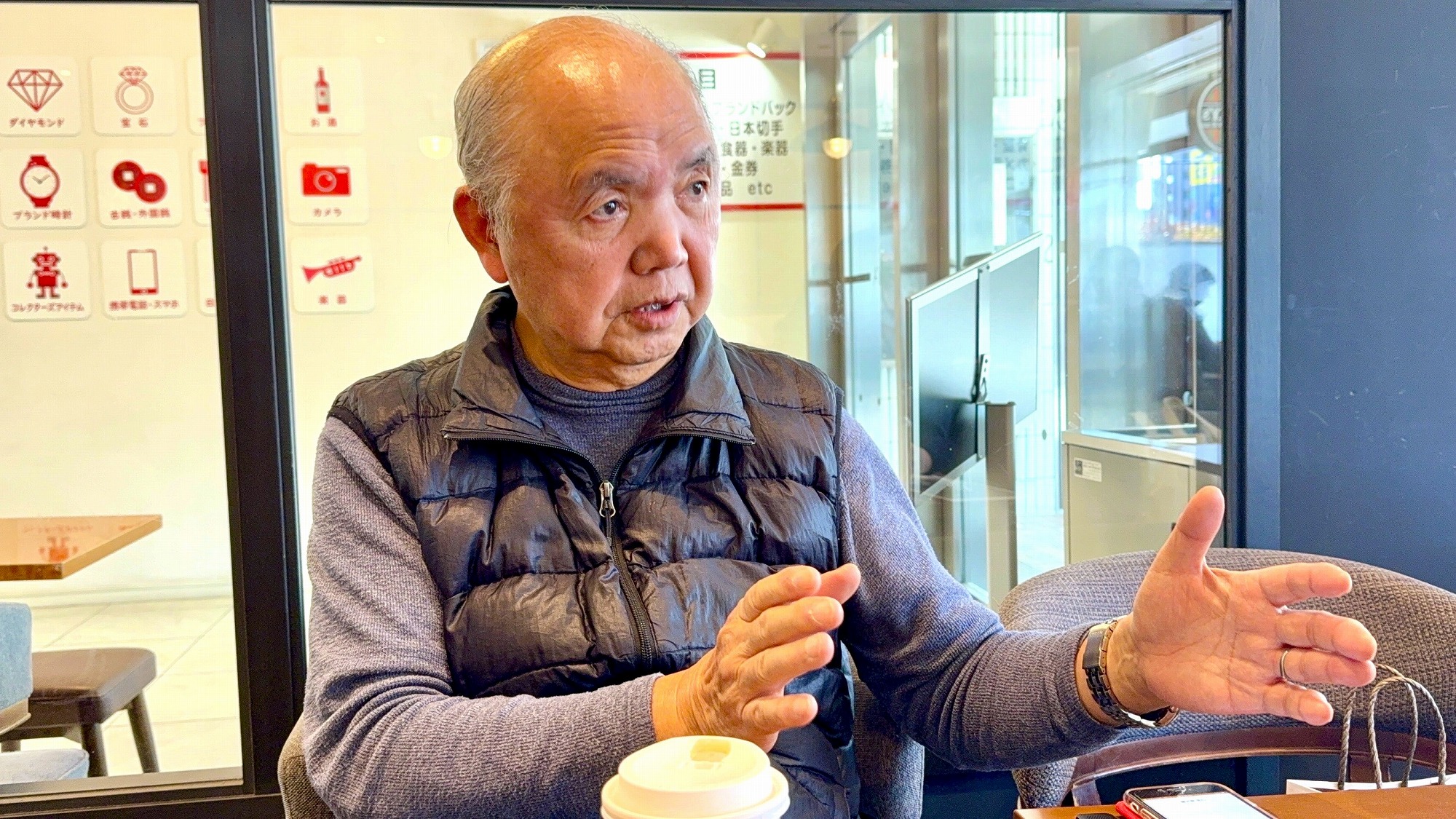
【「逃げない勇気」で世界を股にかける】
職場で周りを見れば、東京大学、京都大学、一橋などの国立大出身者達がゴロゴロいるわけです。私学出身者は少なかったです。でも私は委縮しませんでした。なぜかというと、大学時代が学園紛争の時代で、そのおかげもあって西洋哲学、東洋哲学を人一倍学び、「何のために生きるか」「どうやって自分は生きたらいいか」の核みたいなものを持ち得ていたからです。
かつ、職場では、できる人ばっかりで、こっちは謙虚だから色んなものを学べるわけです。そうこうするうちに、20代後半でバンコクに駐在を命じられました。
バンコクから帰ってきて5年経ったら、人事課長から突然呼ばれて、「アジア開発銀行に1つポストがある。今度面接を受けろ」と言われました。でも前々から、世界銀行とアジア開発銀行で勤務して帰ってきた先輩達から「とにかく競争が激しくて、よっぽど心臓が強くないと務まらない」と聞いていたので、「希望も出してないし、心臓も強くないので、私は向いてないと思います」と言ったら、人事課長から「断ると思ってないので、よく考えろ」と。それで週末考えて、「やっぱりここは逃げちゃいけない」と。皆さんにも卒業の時に「辛いことから逃げない勇気」を喋ったじゃないですか。その逃げない勇気を発揮して週明けに「受けます」って受けたら、第1次面接(東京)と第2次面接(マニラ本店)に受かったんです。
僕は留学してないわけですね。アジア開発銀行にいた約4年近くの経験がその後の自分をめちゃくちゃ支えていたと分かるんですよ。アジア開発銀行はアジアの人も多いけど、専門スタッフには主要出資国のヨーロッパやアメリカの人が過半数いて、そういう人達と喧々諤々とやるわけです。しかも給与面でも駄目な奴はベースアップ0とか、辞めてゆくとか。そういう中で生き延びて、給与レベルを毎年上げているうちに、対外国人が怖くなくなって、英語ももちろんそうです。その経験は自分をものすごく強くしました。それがマニラでの話です。
帰ってきて、また5年経ったら、「今度はインドに行け」と。その時にインドの担当課長をしていたんですけど、ちょうどインドが1991年に経済改革を行って、それまでずっと社会主義で来ていたけど、1991年の湾岸戦争を契機に、独立以来最大の経済危機となり、市場経済化を始めたタイミングでした。担当課長としてインドに対する緊急支援の円借款をまとめたりして、それでインドに赴任して、本格的に数多くのインド官僚達と関わって、それでまたインド人を説き伏せる肝と能力が身に付きました。インド人には結構驚かれましたね。

〈90~92年は東京でインドを含む南西アジア担当課長、92~94年はインド事務所所長を務めました。当時の組織名は海外経済協力基金(OECF)。61年創設で円借款を専門に担当していた政府機関です。その後99年から国際協力銀行(JBIC)に、更に2008年から国際協力機構(JICA)に組織統合になりました。写真は2018年夏のゼミのインド研修で、元デリー事務所スタッフの2人と会った時です〉
そういう経験をして帰国して、南アジアや中東辺りの担当部長をやった後に突然、「本部で円借款業務全般を統括する部長をやれ」と言われ、国会やら色々あってヘトヘトでした。
そうしたなか2002年のある日、役員から役員室に呼ばれて行ったら、「君、2か月後からパリに行ってもらう」と言われたんです。それは2002年の初夏で、当時はミレニアムデベロップメントゴールズ、MDGsで世界中がアフリカをどうするかを考えていた時でした。
「君にはアフリカ全域を担当してもらう」と。フランスの元植民地がアフリカにいっぱいあり、フランス語圏の情報が集まるので、「世界銀行もOECD(経済協力開発機構)もアフリカにますます注力する。だからパリにいて、パリからアフリカ中を回ってほしい。日本として今後どうやったら円借款でアフリカの支援ができるか考えてほしい」と言われました。結局1年3か月しかいませんでしたが、その間に1番貧しいエリアのサブサハラアフリカ13か国を回りました。宿題の対アフリカ支援スキームは、帰国時に日本政府に私案が採用され、G7でも公表され、20年後の今も運用されています。
【「よくあるパターン」で念願の“本ちゃん”へ】
その後、2005年の9月に国際協力銀行(JBIC)を退職しました。最後は同銀行の開発金融研究所の所長でした。実はその退職1か月前に突然ある知人から電話がかかってきていたんです。相手はアジア開発銀行で時期がちょっと被っていた人で、横浜国大の大学院の研究科長になっていました。その人から「橘田さん、客員教授で科目担当をやってくれないか」と言われて、「いいですよ」と引き受けました。
なんですぐに客員教授ができたかというと、インドから帰ってきた翌年の1995年秋に、青学の経済学部でゼミの先生だった原教授から「橘田君、1度講義してくれないか」と言われて、9号館の大教室で、日本の開発援助について話をしたことがあったんです。
講義後に先生から「橘田君、お昼空いてますか?」って誘われて。青山キャンパス近くの高そうなレストランに案内されて、そこにいた経済学部のたくさんの教授達から色んなことを聞かれました。それからしばらく経ったら原教授から電話がかかってきて「君、面接に合格したから、来年1996年度から青学で非常勤をやってくれないか?」と言われ、各国経済論をやりました。ウィークデイでは忙しくてできなくて、土曜日に昼間部・夜間部合同の科目を担当しました。
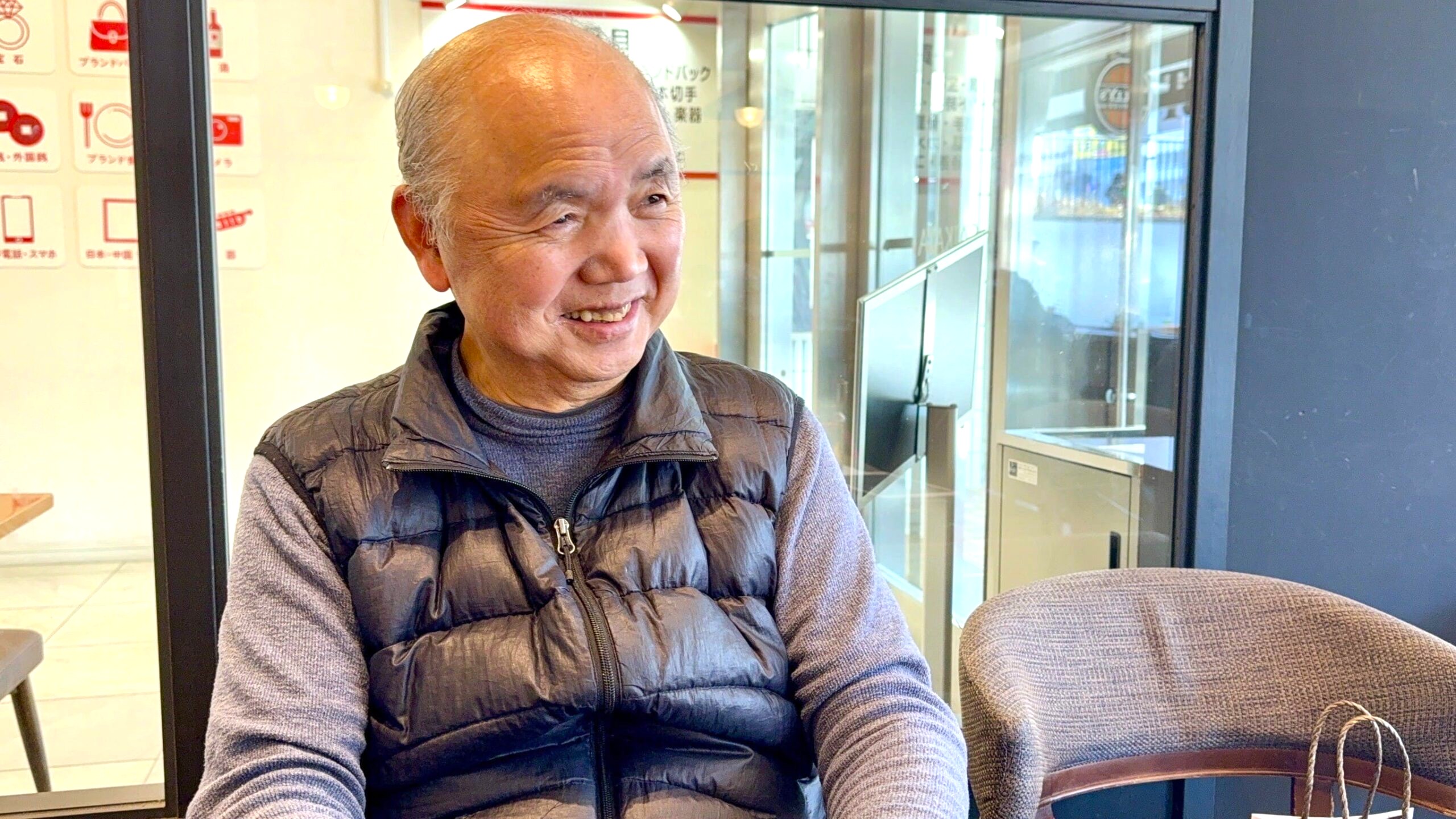
原先生からは「君は大学を卒業する前から『第1の人生を退職したら大学の先生をやりたい』って言ってたじゃないか」と言われたのですが、大卒前から本当にそう思っていたんです。なぜ思っていたかというと、ここ大事なんだけど、自分が大学で勉強して人生で初めて学ぶことの面白さを知ったんです。それと同時に、色んな哲学や思想史などを勉強して精神力が強くなったんですよ。自分はどうしたら生きていけるか、「核」を持ったんです。大学の時に、強く生きる術を発見するキッカケを与えてもらうことが重要なんです。そのキッカケを与えられるような仕事ができたらいいなと思って、第2の人生で大学に行きたいと思ったんです。
それで1996年から青学大で非常勤講師をやっていて、10年目の2005年に「横浜国大の大学院で客員教授をやってくれないか」と言われたんです。既に私は1年間分の講義のネタがあるから、「いいですよ」と引き受けて、横浜国大の大学院で教え始めました。でも客員教授って非常勤と基本的に変わらないんですよ。フルタイムの“本ちゃん”じゃないんですよ。
「フルタイムでやりたいな」と思っていたなかで、私の専門分野で4つぐらい大学の公募があって、国立大や私大を受けたのですが、駄目でした。「なんで駄目なんですかね?」って知人のある先生に聞いたら、「だって橘田さん、もうすぐ60歳じゃないですか。しかも留学してないし、博士号を持ってないでしょ」って言われて、「そうか駄目か」と。
そうこうするうちに、筑波大学の募集の情報が来て、これが駄目だったらもう諦めようと思って受けたら、受かったんです。
それで筑波大学で、教授に加えて、筑波大学の国際化をさらに進める新設の国際部の部長も兼任する教授の仕事を始めました。でも筑波大学は、生徒は良いんだけど、私の住居がある藤沢からは遠い。大学の宿舎を与えられたんだけど、年長者にはやっぱりしんどいわけです。
そんななか、筑波大3年目のある日、同大学のある先生が「青学の大学院で、2011年春から社会人留学生を受け入れる英語だけの修士プログラムを始めるので、先生を募集している」と教えてくれました。自分は筑波大学で、社会人留学生の修士プログラムで教えていたし、学部でも英語で教える科目も担当していたので、募集の情報を教えてくれた先生が「推薦するので受けませんか」って。その時、ちょうど筑波大の国際部長の仕事のきりも良かったし、青学は母校なので、「はい」と言って青学に応募したのが2011年の3月です。

〈地球社会共生学部開設後も、毎週金曜に青山キャンパスで大学院の社会人留学生(全員が途上国の政府職員達)への授業を担当していた頃です〉
【当時学長の仙波先生から電話が!「クビかな?」ドキドキして会いに行ったら…】
それから2年後の2013年の春、大学院の特任教授3年目の時です。突然、当時学長を務めていた仙波先生の学長秘書から電話がかかってきて、「学長がお会いしたいと言っています。ご都合の良い時間に」って。こっちはぺいぺいの特任教授でしょ。会ったこともない学長の秘書から電話がかかってきて、いきなり「学長が会いたいと言っています」って言うから、クビかな?「もうそろそろ、やめていただきたい」って言われると思ったわけです(笑)。
歳も歳だし。2013年だから64歳。恐る恐る学長室へ行ったら、仙波先生と平澤先生がおられて、そこで仙波先生が「今度、相模原キャンパスに社会科学系の新しい学部を作ります。グローバルに活躍できる学生を育てたい。いずれは留学生も呼びたい。橘田先生は筑波大学で国際部長をされて、筑波大学の国際化推進の仕事をされたと聞いています。開設準備委員会を作るので、そのメンバーになってもらえませんか」と言われて。こっちはもうクビじゃなくてホッとしたこともあり(笑)、「そういうことでお役に立つのであれば、是非やらせてください」と言って、お引き受けしました。
それで1年半ほど経って、2014年のある日、平澤先生が「文科省から許可が降りました。これから2015年4月入学の学生を募集します。ついては、2015年の4月から開設準備委員会の先生は淵野辺に移っていただいて、そこで教員になっていただきます」と。それで2015年の4月に向けて、色んな準備でタイの大学に行ったり、マレーシアの大学に行きました。

〈地球社会共生学部に移る前(青学大の大学院経営学研究科の特任教授)の2014年頃です。この期では私のゼミで修論指導した3人のうち、ケニアからの院生が翌年の修了式で研究科でトップの総代に選ばれました。指導教員としても大変誇らしかったです〉
※橘田先生スペシャルインタビュー第2回終了(全3回)


